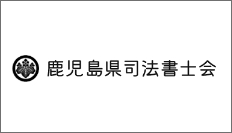うみかぜ総合法務事務所(司法書士・行政書士・社労士)
司法過疎への取組み~情熱を持ち続けること/鹿児島奄美(徳之島・奄美大島・沖永良部島・与論島) の法律相談・登記・相続手続き・会社設立
司法過疎への取組み~情熱を持ち続けること
司法書士の柏村です。
先日,司法過疎に興味を持つ方から応募がありました。
ふと思い返せば,司法過疎への取組み,島嶼地域での活動は,常に念頭にありながら,すでに徳之島で10年近くを迎えています。
その成果?その情熱は? 自問してみようと思います。
Q1 法律専門職は育ったか?
どうだろう。△かな。
司法書士有資格者が2名加わり,その後巣立っていった。司法過疎地で求めれるいる司法書士像を知り,感じてもらう機会にはなったと思うが,直接的な,司法過疎解消に向けた広がりには至っていない。
Q2 受験生への支援は,成果を挙げたか?
これまで受験生を受け入れてきたが,合格者を輩出していない。現在も,司法書士受験生,社会保険労務士の受験生のスタッフにいる。今年が受験2年目,3年目を迎えることになるので,その成果が問われる時期にある。
Q3 人材募集や育成はできているか?
一時,人材募集について,島外への発信を中心にしていた時期がある。わざわざ島にやってくるのだから,覚悟があるだろうと考えていた。そして,有能な人材も多いのではないかと感じていた。一方,最近は,長期雇用,安定した事務所運営には,島内出身者のスタッフがより重要だと考えている。地元スタッフがいることで,地元意識が芽生え,さらには,「島に貢献したい」という気持ちにもつながっているように思うから。
Q4 総括
同じ時期に奄美で司法過疎解消に取り組んでいた弁護士の鈴木穂人氏(そらうみ法律事務所 http://soraumi-law.jugem.jp/ )は,その後,事務所を法人化し,さらに,支店を広げている。
その差は何のか。私自身の情熱の差か,そもそも弁護士と司法書士の司法過疎への取組みに差があるのか,まだ検証できていない。
現状は素直にこれである。2歩進んでも,その後に2歩下がる。展開は思うようにはいかない。タネを蒔いて,芽が出て,少しずつ育っても,台風などで折れたり,萎れたりするときがあるように。
2歩進めた分だけ,経験値は上がっているし,成長できていると思いたい。立ち止まるときも,疲れるときもあるけれど,いろいろな想いを少しでも形にできるように,また歩き出そう,そう思っている。
Q5 これから
昨年,司法書士法に使命規定が定められ,それに伴って,現在,司法書士倫理が見直されている。司法書士に求められるものは何なのか,その存在意義を改めて考える時期にある。司法過疎地での活動もしかりで,司法書士が少ないから単純に増やせばいいというものではなく,地域のニーズに応えられる人材とは何か,どうしたらそのような人材が育成できるか,司法書士業界内で活発な議論と積極的な取組みが必要だろう。うみかぜ事務所での業務は,他の司法書士のそれに比べ,特段特別なものではないが,司法過疎地での経験として発信できる立場にある。司法書士業界や司法過疎地での活動に興味をもっている司法書士の一助となれればと思う。